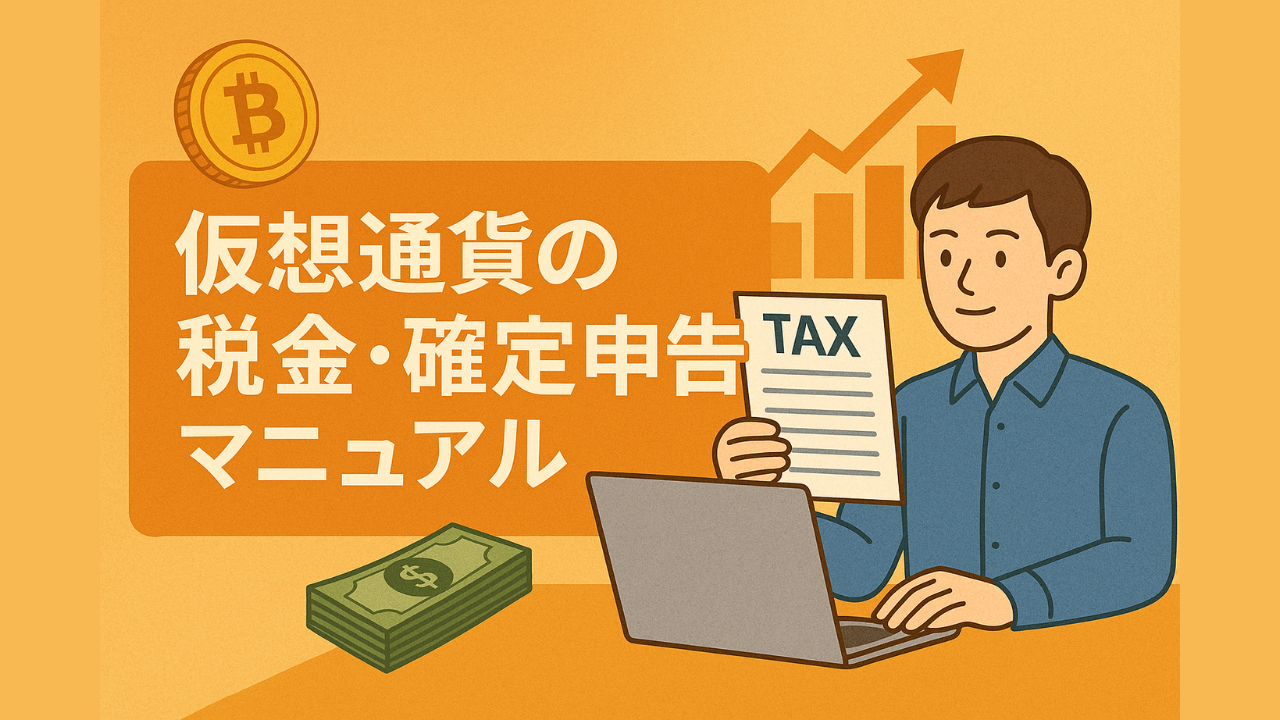仮想通貨で利益を出したら、避けて通れないのが「税金」と「確定申告」。
利益が出たのに申告しないと延滞税や重加算税など、後で大きな負担になる可能性もあります。
この記事では、最新ルールに基づいて、仮想通貨に関する税金の種類や、確定申告の手順、損益計算に便利なツールをご紹介します。しかしながら、筆者自身は税理士ではありませんので「大枠の解説」となります。
個別事例や詳細は税理士やお近くの税務署へご相談ください。
リンクから商品・サービスを申し込まれた場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. 仮想通貨にかかる税金の基本
仮想通貨で得た利益は、基本的に「雑所得」として課税対象になります。
たとえば以下のような取引は課税対象になります。
- 仮想通貨を日本円に換金した
- 仮想通貨で別の仮想通貨を購入した
- 仮想通貨で商品やサービスを購入した
- マイニングやステーキングで報酬を得た
- エアドロップで仮想通貨を受け取った
これらの利益が「年間20万円」を超えると確定申告が必要です。(給与所得者の場合)。

2. 仮想通貨の課税タイミングと計算方法
仮想通貨は「取得価格」と「売却価格」の差額が利益になります。
これを総平均法や移動平均法などで計算します。
たとえば、簡単な計算のイメージで言うと以下の通りとなります。
- ビットコインを30万円分購入した
- ビットコインが連日値上がり
- 利益を確定するため後日50万円で売却した
- 利益は「50万円 – 30万円 = 20万円」
利益が出た年の翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

3. 申告方法と必要書類
仮想通貨(暗号資産)の利益申告には、以下の書類が必要になります。
- 年間取引報告書(各取引所でダウンロード)
- 損益計算レポート
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 本人確認書類(マイナンバーなど)
確定申告は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで作成・提出できます。

4. 仮想通貨に使える損益計算ツール
手動での損益計算は煩雑です。
以下のような仮想通貨損益計算ツールというものも存在しますので、これらを使うと正確かつ効率的に計算ができます。
税理士への相談とこれらのツール活用は視野にいれておくのがベターです。
| ツール名 | 特徴 | 対応取引所&公式サイト |
|---|---|---|
| Cryptact | 日本最大級の仮想通貨損益計算ツール。 仮想通貨の確定申告をもっと簡単に。 |
Coincheck, bitFlyerなど Cryptactサイトはこちら |
| Gtax | 自動インポート機能あり。税理士連携可。 一部機能が無料で使えるフリープランもアリ。 |
GMOコイン, bitbank, Bybitなど Gtaxサイトはこちら |
| Coinpanda | 英語対応ながらUIがわかりやすい。 ただ、暗号資産初心者は上記2つの方が良いかも。 |
世界中の取引所に対応 coinpandaサイトはこちら |
5. 税金対策のポイント
税金に関する対策ポイントはまずは以下を押さえておくと良いでしょう。
- 損失が出たとしても翌年以降に繰り越せない(雑所得のため)
- 利益が出た年は、医療費控除・ふるさと納税・iDeCoなどで税負担を減らす
- 副業収入などと合算して課税されるので注意
- 複数の取引所の履歴は一元管理しておく

6. よくある質問(FAQ)
- Q. 利益が20万円以下なら申告不要?
- A. 給与所得者で年収2000万円以下かつ副収入が20万円以下なら申告不要。ただし住民税の申告は必要な場合があります。
- Q. エアドロップやキャンペーンでも税金がかかる?
- A. はい。受け取った時点の時価で所得が発生します。
- Q. NFTやDeFiの収益も申告対象?
- A. はい。NFT売買やDeFi運用で得た利益も雑所得として課税対象です。

まとめ
仮想通貨は利益が出るとうれしい反面、「税金」で思わぬ負担になることもあります。
正確な税務申告が行えることは大切ですので、最新の法律やルールを押さえ、損益計算ツールの活用もご検討ください。
特に、取引量が多い方や海外取引所を使う方は、プロの税理士に相談するのもおすすめです。
- ▶ 関連記事:仮想通貨取引所おすすめランキングと選び方
- ▶ 関連記事:ステーキングで資産運用する方法はこちら